皆どう使ってる?やってみたくなる えんギフトの活用事例
皆どう使ってる?やってみたくなる えんギフトの活用事例
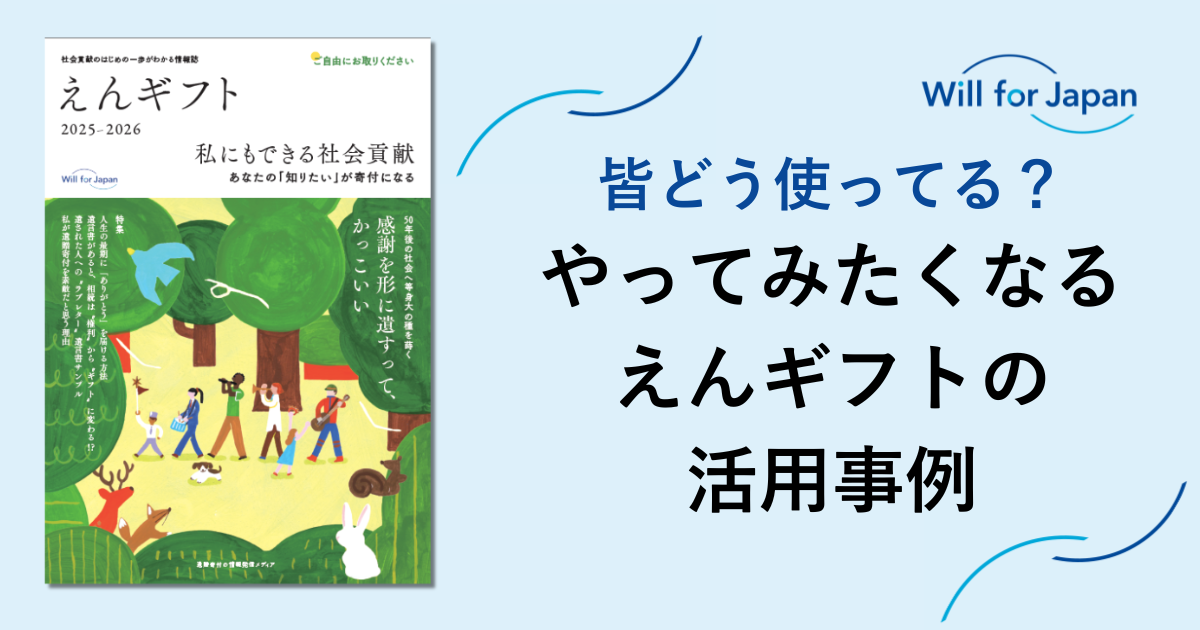
遺言や相続の話題になると、「難しそう」「まだ先のこと」と感じてしまう方は少なくありません。でも実際には、「自分の想いをどう残すか」「誰にどんな形で託すか」を考えることは、これからの人生を前向きに生きることにもつながります。
私たち日本承継寄付協会が発行している『えんギフト』は、そうした“想いを形にする選択肢”として、遺贈寄付の実例や寄付先団体を紹介する情報誌です。近年、士業や金融機関、終活支援の専門家など、さまざまな現場で相談ツールとして活用が広がっています。
ここでは、実際に『えんギフト』を活用してくださっている専門家の方々の事例と、協会からのポイントをご紹介します。“相談の場でどう使えるか”をイメージしながら、ぜひご覧ください。
事例① 相続人がいない方へ、相続の選択肢として切り出す
■おひとりさまのトータルサポートを行うAさんの事例
当社では、遺言書の作成にあたり、まずお客様に法定相続人についてご説明します。おひとりさまのご相談が多く、法定相続人がいない場合は財産の行き先に悩む方が多いため、選択肢のひとつとして遺贈寄付をご紹介し、えんギフトをお渡ししています。
次回の面談までに寄付先をご検討いただいたり、一緒に寄付先を検討したりし、これまでに150冊ほど活用してきました。
お客様の関心はご自身の終活のことで、遺贈寄付は沢山ある決め事の一つにすぎません。そんな中で、えんギフトがあることで信頼できる寄付先の見通しが立ち、お客様のご負担も軽減されます。
遺言作成を前に進めるうえで、えんギフトは欠かせないツールです。
日本承継寄付協会からのPoint!
当協会へのご相談の中には、「遺贈寄付」という選択肢を知らず、財産の行き先に長年悩んでいたという方もいらっしゃいます。Aさんによれば、遺贈寄付を選択肢の一つとして伝えても、お客様から否定的な反応はほとんどないとのことです。
お伝えすることはお客様の選択肢を広げるメリットになるという観点で、お伝えしてみてはいかがでしょうか。
事例② 親世代へ遺言書作成を後押しするツールとして活用する
■相続全般の相談を受けるBさんの事例
当法人では相続人であるご家族からのご依頼が多くあります。
親御様に遺言書を作成してもらうきっかけとして、えんギフトを相続人の方にお渡しするケースが増えています。これまでに約120冊を活用してきました。
たとえば、50代の娘さんにえんギフトをお渡ししたところ、後日、80代のお父様に遺言作成を勧めるきっかけとして活用されました。
えんギフトがあることで、遺贈寄付についても自然に話題にしやすく、安心してご案内できています。
日本承継寄付協会からのPoint!
弊協会が行った調査では、親族による少額の遺贈寄付について、約8割の方が好意的な印象を持っていることが分かっています。
「お世話になった場所に感謝を込めて」「関心のある分野を少しでも応援したい」といった気持ちを、無理のない範囲でかたちにできることが、相続を“権利”として分けるだけでなく、“ギフト”として贈るという前向きな選択につながり、遺言書作成の後押しになることもあります。
事例③ 遺贈寄付のイメージを持ってもらうために渡す
■死後事務委任も行う司法書士Cさんの事例
当法人では死後事務委任も行っていますが、最終的な財産の遺し先まで明確にされていないお客様が多くいらっしゃいます。
お客様に納得できる財産の遺し先を見つけていただくために、選択肢の一つとして遺贈寄付をご提案しています。
遺贈寄付を初めて知る方も多いので、具体的なイメージを持っていただくためにえんギフトをお渡ししています。
例えば、ペットを飼っている方には、遺贈寄付とあわせてペットの引き渡し方法もご相談いただくなど、複合的な課題の解消にもつながっています。
また、小規模団体への寄付を希望される場合には、予備的にえんギフトの掲載団体を遺贈先とする形で活用しています。
日本承継寄付協会からのPoint!
えんギフトに掲載されている団体は、経営の健全性や社会的インパクトなど、4つの基準に基づき当協会の審査を通過しています。いずれも遺贈寄付の受け入れ実績が豊富で、安心してご紹介いただける団体です。
また、寄付先と聞くとテレビCMで見るような団体しか思い浮かばない方も多くいます。えんギフトを通じて幅広い分野の団体を知っていただくことが、ご自身の思いや経験を振り返るきっかけにもなります。
事例④ カタログ感覚で読んでみて、と気軽に渡す
■行政書士Dさんの事例
お客様に遺言の大切さ、必要性を理解していただくための、一つのきっかけとしてえんギフトを活用しています。
「ふるさと納税のカタログギフトのような感覚で読んでみて」と声をかけ、えんギフトを気軽にお渡ししています。ふるさと納税は馴染みのある言葉なので、すんなり受け取っていただけます。
日本承継寄付協会からのPoint!
えんギフトは柔らかなタッチの表紙で、読み物としても楽しめる内容です。「必ずしなければならないもの」ではなく、「こんな冊子がある」と、気軽にお渡しいただけます。ドラッグストアや美容院などにも設置され、好評をいただいています。
いかがでしたでしょうか。
遺贈寄付という言葉は、まだ一般的ではありません。ですが、『えんギフト』をきっかけに「こんな形もあるんだ」と知ることで、多くの方が“自分らしいお金の残し方”を考えるようになっています。
専門家の方にとっても、ご相談者との会話を自然に広げるツールとして役立つ場面が増えています。
「冊子を渡すだけで話が前に進んだ」という声も多く、えんギフトが“人と想いをつなぐ架け橋”になりつつあります。
ぜひ、「えんギフト」を皆さまの現場でもご活用いただけましたら幸いです。

