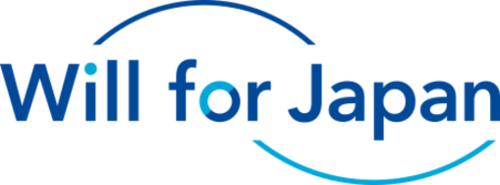地域に飛び込み、地域とともに成長する若者を後押しする奨学金を遺贈寄付で支える/さとのば

特定非営利活動法人 さとのば
日本全国をキャンパスに、学生が4年間で4つの地域を旅し、それぞれの土地で暮らしながら学ぶ新しい市民大学「さとのば大学」。地域に入り、実践的な活動を通じて学び合う「越境して学ぶ学生」たちに対し、奨学金の給付や学習環境づくりの支援を行っています。
さまざまな地域と若者が出会い、触れ合う機会をつくることで、地域社会への関心を育み、地域が抱える課題の解決にもつながることを目指し活動を続けています。未来を担う若者と地域の未来をともに拓き、新しい学びの形を模索する、さとのば大学理事長の信岡良亮さんにお話を伺いました。(取材日:2025年2月3日)

信岡 良亮さん
1982年生まれ。大学卒業後東京のITベンチャーへ勤務。幸福な未来への疑問から退職し、島根県海士町に移住。持続可能な未来を目指し起業し、現在はさとのば大学を運営。
目次:
1. キャンパスは日本全国。越境して学ぶ若者が育つ、新しい学びの形
___まず「さとのば大学」の取り組みについて教えていただけますか。
さとのば大学は、1年ずつ日本の地方創生の先端地域に留学し、4年間で4つの地域をめぐるという地域を旅する市民大学です。現在、北海道から鹿児島まで、日本全国14ヶ所の地域と連携しています。学生は毎年異なる町に「留学」し、その地域の中で暮らしながら、社会の課題を解決するための学びを深めていきます。私自身は、島根県の海士町という場所にずっといて、地方暮らしで見えてきた社会課題、地域の中に入っていくことの楽しい部分としんどい部分を見てきました。その中で地域に実際入りながらの人材育成をすることが、日本の未来に繋がるのではないかと考えるようになりました。

全国各地に広がる在校生や地域共創領域のトップランナーである講師陣とオンラインで繋がり、理論のインプットと対話で学びを最大化し、通信制大学とのダブルスクールで、学士号の取得を目指すことのできる体制を整えています。
現在の少人数だからこそできるカリキュラムもありますが、ある程度の人数がいるからこそ実現できることもあるので、いまはひと学年64人という規模感を目標にいろいろな取り組みを重ねているところです。

___「市民大学」とされたのはなぜですか。
私たちの取り組みたい学びの形、プロジェクトを中心とした学びをつくろうと思うと、文科省認定の学校ではなく「私塾」のようなものになります。しかし、私塾となると、通常の大学のように学士号を取得することができません。
学士号の取得に重きを置くかは人それぞれですが、私塾であるということが選択のネックになるのであればそれを解消したい考え、通信制大学のオンライン講義を同時に履修することで学士号の取得を目指すことができる体制を新潟産業大学経済学部の通信教育課程「managara」と作りました。
また、私塾という位置づけの場合、一般の奨学金制度を利用することができないという問題があります。そこで、経済的に苦しいけれど学びたいという意欲の高い若者たちのために独自の奨学金制度(授業料減免制度)を用意しています。
___今はどのような方たちが取り組みを支援されているのでしょうか?
いろいろな方がいらっしゃいます。社会起業家の方や学生たちを受け入れてくださっている地域の方々、大企業の役員の方もいらっしゃいます。さとのばを通じて知り合った方や、クラウドファンディングでつながって支援者になってくださった方などさまざまですね。
___将来的に遺贈寄付を受け取ったら取り組んでみたいことはありますか。
奨学金を拡充し、今よりも多くの学生に届けられるかたちにしたいです。ご寄付は基金として運用し、継続的な奨学金として活用していきたいと考えています。海外の大学では、学生からの授業料収入ではなく、基金の運用益が収益の柱になっているケースも多いと聞きます。大学の運営は、本質的には未来への投資であり、多様な学びを提供できることが重要です。そのためにも、学生や保護者の経済的負担を奨学金によって軽減し、学びの可能性を広げていけたらと考えています。
2. 自然に手を差し伸べる力を、地域の中で育む
___活動を続けてきて感じている課題はありますか?
自分たちの活動を伝えていくことの難しさを感じています。学生たちや地域の変化というのは、長いスパンで見なければなかなか分からないものです。例えば、私は保護猫を飼っているのですが、今の猫の様子だけを見ても、保護したときと比べてどれぐらい慣れてきたかということは分からないですよね。でも、毎日見守ってくれている人には前後の変化が分かる。私たちの活動も同じで、長く見守ってもらうことで初めて、やっていることの意味や価値が分かる。そういう時間のかかるものだということを、取り組めば取り組むほど感じています。
日本財団が実施したアンケートで「日本の若者は他国の若者に比べて自己肯定感が低い」という結果が出ているのですが、さとのば大学の学生に同じアンケートをとると、平均よりも20%ほど高い結果が出るんです。
それは、地域に入って、たくさんの大人たちと関わっているからではないかと。魅力的な大人たちにやりたいと思ったことを受け止めてもらえることで、自分も社会に参加できる、参加しているという想いが育ち、結果、自己肯定感も高まるのではないかと思うのです。そのことを、もっと多くの人に伝えていけたらと考えています。

___ずばり「さとのば」らしさとは、どのようなところにあるのでしょうか。
人と接するのが苦手だった学生の話をさせてください。彼は、地域のフリーペーパーを作るプロジェクトに参加していたのですが、その制作を通してたくさんの地域の高齢者と交流することになります。
その交流の中で、とある高齢の方から携帯電話をスマホに切り替えたいけれど、携帯ショップに行くこともできないという話を聞きました。すでに孫のような存在になっていた彼は、その方のスマホの切り替えをお手伝いしたそうなんです。しばらくしてまた話を聞いたら「使い方が難しいから元に戻したい」と言われて、またいろいろやり取りをした結果、分かりやすい操作マニュアルがあれば使えそうだということが分かった、と。そこで今は、フリーペーパー作りで身につけた編集力を生かして、スマホの使い方マニュアルを作っているそうです。
私たちの取り組みは、何か社会全体を大きく変革するような活動というよりも、等身大の社会接続というところにあります。息を吸って吐くように、自然に誰かの幸せに還元できるような取り組みです。スマホを通じた高齢者と若者の関わりもそうですが、例えば、混雑した電車内でベビーカーを降ろすのをちょっとサポートするようなことも同じだと思うんです。簡単そうで、意外と勇気のいること、周りがなかなか手を差し伸べない中、自然と手が伸びるということができる若者が育つのが、さとのばらしさなのではないかと思います。

3. 遺贈寄付に興味を持っている方へのメッセージ
___遺贈寄付に興味を持っていらっしゃる方にメッセージをお願いします。
さとのば大学の取り組みに関心を持っていただきありがとうございます。私たちの活動は、なかなか「成果」のようなものが見えづらく、一見すると分かりにくいかもしれません。
私たちの活動は未来への種まきのようなものだと考えています。もしよろしければ、学生たちの成果発表の場に一度足を運んでみてください。学生たちが、試行錯誤を繰り返しながら、身一つで地域に飛び込み、自分自身を生かして社会と接続をしていく、その一人ひとりの物語は本当に美しいものだと感じています。
同時に、未来の世代に何かを託すということは、人としてとても豊かなあり方だとも思います。皆様に託していただいた想いとお金を、私たちは必ず未来につなげていきます。皆様の想いが、学生の未来、地域の未来と、二重にも三重にも価値を生み、社会に波及していくような、そんな使い方をしていきたいと考えています。
4. 寄付の使い道について
皆様のご寄付は、さとのば大学の運営や、より多くの学生に学びの機会を届けることができるよう、地域での活動資金や奨学金制度の拡充などに大切に活用させていただきます。包括遺贈や不動産の寄付をご検討の場合は、事前にご相談ください。
・遺贈寄付のお問合せフォームはこちら
5.団体紹介
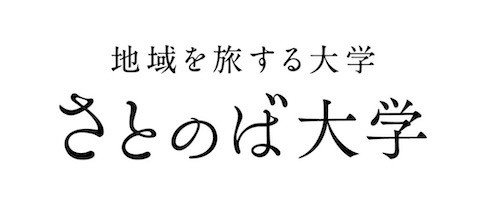
・団体名
特定非営利活動法人さとのば
・所在地
東京都千代田区神田錦町3‐21 ちよだプラットフォームスクウェア1345
・代表者
代表理事 信岡 良亮
・設立年
2023年
<ミッション>
地域とつながりながら学ぶ、新しい教育モデルの創出
<活動内容>
1. 地域を旅する学生への奨学金給付
さとのば大学で学ぶ学生に、学費や取り組む活動の費用の一部を給付します。多くの学生は、生活費や活動費を地域内でのアルバイトで捻出しています。奨学金給付により活動・挑戦の時間を確保することができます。

2. 地域を旅する学びの体験機会の提供
「地域で何が学べるの?」この答えは、一度地域に触れてみることで、感じることができます。高校・大学生向け地域留学体験短期プログラム「Learning Journey」の提供を通じて、地域での学びの体験と、学生と様々な地域との縁をつくっていく機会づくりをしています。

3. 地域での未来づくりを促進する拠点“さとのば寮”の設置
地域内での様々なプロジェクトを促進するのは、地域の人や学生が集まり議論することができる共創スペースです。ご寄付を基に、移住先の各地域に、学生たちが住み、地域の人と交わる「地域づくりの共創場所」を併設する寮を設置したいと考えています。